PCの設定の覚え書きを中心に。
旧共産圏のカメラ、アウトドアも少しずつ。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
この暑さで無線LANの親機が逝ってしまった。
(-人-)
ハイパワーに買い換える。さすがに快適。
電波状況を調べるため、ubuntuにkismetをインストールした。
2008版ならSynapticパッケージマネジャーでインストールできるのだが、最新の2010版をインストールするのにちょっと苦労したので、メモ。
Ubuntu10.04にkismetをインストールする。
適当なところからKismet 2010-07-R1をダウンロード、端末より展開してできたフォルダー(kismet-2010-01-R1)に移動し、管理者となる。
# cd kismet-2010-01-R1
# ./configure
途中でエラー。
configure: error: Neither uclibc uClibc++ or standard gcc stdc++ libraries found.
色々、足らないらしい。
# apt-get update
# apt-get install build-essential
# apt-get install libstdc++6 libstdc++6-4.3-dev
再開する
# ./configure
再びエラー
configure: error: Failed to find libcurses or libncurses. Install them or disable building the Kismet client with --disable-client. Disabling the client is probably not something you want to do normally.
おまじないが必要。
# apt-get install libmagickwand-dev
# apt-get build-dep kismet
また、再開する。
# ./configure
Configuration complete. Run 'make dep' to generate dependencies
and 'make' followed by 'make install' to compile and install.
今度はうまくいった。
仰せの通りにmakeする。
# make dep
# make
# make install
インストール終了
$ sudo kismet
無事、起動した。
(-人-)
ハイパワーに買い換える。さすがに快適。
電波状況を調べるため、ubuntuにkismetをインストールした。
2008版ならSynapticパッケージマネジャーでインストールできるのだが、最新の2010版をインストールするのにちょっと苦労したので、メモ。
Ubuntu10.04にkismetをインストールする。
適当なところからKismet 2010-07-R1をダウンロード、端末より展開してできたフォルダー(kismet-2010-01-R1)に移動し、管理者となる。
# cd kismet-2010-01-R1
# ./configure
途中でエラー。
configure: error: Neither uclibc uClibc++ or standard gcc stdc++ libraries found.
色々、足らないらしい。
# apt-get update
# apt-get install build-essential
# apt-get install libstdc++6 libstdc++6-4.3-dev
再開する
# ./configure
再びエラー
configure: error: Failed to find libcurses or libncurses. Install them or disable building the Kismet client with --disable-client. Disabling the client is probably not something you want to do normally.
おまじないが必要。
# apt-get install libmagickwand-dev
# apt-get build-dep kismet
また、再開する。
# ./configure
Configuration complete. Run 'make dep' to generate dependencies
and 'make' followed by 'make install' to compile and install.
今度はうまくいった。
仰せの通りにmakeする。
# make dep
# make
# make install
インストール終了
$ sudo kismet
無事、起動した。
PR
netatalk2.1のインストールを行う。
以下の4つのインストールが必要。
それぞれダウンロードして展開、configureして、makeして、インストールする。
作業は/tmpで行うこととした。
1: Berkeley DB(BerkeleyDB.4.7)
2: OpenSSL(openssl-1.0.0)
3: Libgcrypt(gnupg- 1.4.10)
4: Netatalk(netatalk2.1)
4の前に、1、2、3のインストールが必要である。
-----------------------------------------------------------------------------------
BerkeleyDBのインストール
# cd /tmp
# wget http://download.oracle.com/berkeley-db/db-4.7.25.tar.gz
# tar zxvf db-4.7.25.tar.gz
# cd db-4.7.25/build_unix
# ../dist/configure --prefix=/usr/local/BerkeleyDB.4.7
# make
# make install
# rm -f /usr/local/BerkeleyDB
# ln -s /usr/local/BerkeleyDB.4.7 /usr/local/BerkeleyDB
-----------------------------------------------------------------------------------
OpenSSL(openssl-1.0.0)のインストール
4015794 Jun 1 15:46:21 2010 openssl-1.0.0a.tar.gz (MD5) (SHA1) (PGP sign) [LATEST] をダウンロード、/tmpに展開する。
# cd /tmp/openssl-1.0.0a
# ./config
# make
# make install
-----------------------------------------------------------------------------------
Libgcrypt(gnupg- 1.4.10)のインストール
GnuPG 1.4.10 source compressed using bzip2. をダウンロード、/tmpに展開する。
# cd /tmp/gnupg-1.4.10
# ./configure
# make
# make install
------------------------------------------------------------------------------------
Netatalk(netatalk2.1)のインストール
netatalk-2.1.1.tar.bz2 をダウンロード、/tmpに展開する。
# cd /tmp/netatalk-2.1.1
# ./configure --enable-debian --with-bdb=/usr/local/BerkeleyDB.4.7
# make
# make install
------------------------------------------------------------------------------------
netatalkの起動
# /etc/init.d/netatalk start
netatalkの停止
# /etc/init.d/netatalk stop
netatalkの再起動
# /etc/init.d/netatalk restart
新しいサーバーが完成。
sambaをインストールして、ファイルサーバーを作る。
設定。無事稼動。
音楽ファイル用のディレクトリーを作り、MacBookに貯め込んだ音楽を転送。
しかし、一部の曲が転送できない。
一部の項目へのアクセス権がないため、操作は完了できません。
転送できない曲はMacBookのiTunesでリッピングしたもの。
パーミッションを確認しても、書き込めるようになっている。
Macのターミナルにてパーミッションを確認する。
読み書き可能となっているが、パーミッションの最後に"@"が付いているファイルがある。
$ ls -al
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6241544 5 24 22:31 12 Songbird.m4a
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6129244 5 24 22:31 13 Now Is The Hour.m4a
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a
"@"が付いているファイルはすべてsambaに転送不可である。
なんじゃこりゃ?
ちなみにUSBにコピーして、サーバーにコピーすれば移すことはできる。
調べてみた。
$ ls -la@
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a
com.apple.FinderInfo
” com.apple.FinderInfo”はEA (Extended Attributes)と言う、付加情報。
こいつが悪さをしているらしい。
Mac OS Xのバージョンアップ(現在10.6.3)に起因するようだ。
この付加情報は、以下の方法で消すことができる。
$ xattr -d com.apple.FinderInfo "14 Amazing Grace.m4a"
このファイルは、サーバーに転送できる。
今のところの解決方法。
①xattr -d にてEAを消す。 (面倒くさい)
②USBや外付けHDDで移す。 (面倒くさい、サーバー作った意味ないし~。)
③Samba以外の方法でファイルサーバーを作る。 (netatalkを使う。 2.1以上はEAに対応している。でも大変そう)
④Sambaが対応してくれるのを待つ。 (祈る)
頑張って、netatalkをインストールすることにした。
sambaをインストールして、ファイルサーバーを作る。
設定。無事稼動。
音楽ファイル用のディレクトリーを作り、MacBookに貯め込んだ音楽を転送。
しかし、一部の曲が転送できない。
一部の項目へのアクセス権がないため、操作は完了できません。
転送できない曲はMacBookのiTunesでリッピングしたもの。
パーミッションを確認しても、書き込めるようになっている。
Macのターミナルにてパーミッションを確認する。
読み書き可能となっているが、パーミッションの最後に"@"が付いているファイルがある。
$ ls -al
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6241544 5 24 22:31 12 Songbird.m4a
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 6129244 5 24 22:31 13 Now Is The Hour.m4a
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a
"@"が付いているファイルはすべてsambaに転送不可である。
なんじゃこりゃ?
ちなみにUSBにコピーして、サーバーにコピーすれば移すことはできる。
調べてみた。
$ ls -la@
-rw-r--r--@ 1 aaa staff 7547468 5 24 22:31 14 Amazing Grace.m4a
com.apple.FinderInfo
” com.apple.FinderInfo”はEA (Extended Attributes)と言う、付加情報。
こいつが悪さをしているらしい。
Mac OS Xのバージョンアップ(現在10.6.3)に起因するようだ。
この付加情報は、以下の方法で消すことができる。
$ xattr -d com.apple.FinderInfo "14 Amazing Grace.m4a"
このファイルは、サーバーに転送できる。
今のところの解決方法。
①xattr -d にてEAを消す。 (面倒くさい)
②USBや外付けHDDで移す。 (面倒くさい、サーバー作った意味ないし~。)
③Samba以外の方法でファイルサーバーを作る。 (netatalkを使う。 2.1以上はEAに対応している。でも大変そう)
④Sambaが対応してくれるのを待つ。 (祈る)
頑張って、netatalkをインストールすることにした。
自宅のサーバーが手狭になってきたため、作り替えることにした。
GA-D510UDと2TBのHDD2台でRAIDを構成。
GA-D510UDはmini-ITXのマザーボードで、CPUはAtomD510である。
サーバー兼サブマシンにするため、デスクトップも使えるようにOSはUbuntu9.10にした。
GA-D510UDはRAIDが付いていている。
これが誤算。
M/BでRAIDを組めるのだが、それにアクセスするのにはドライバーが必要。
そのドライバーがWindows用しかなかった。
GIGABYTEさん、たのむよ・・・。
さっさと諦めて、ソフトRAIDとする。
32GBのSSD(SP032GBSSD650S25)があまっていたので、ここにシステムをインストールする。
以前、Windowsを入れたら、プチフリ頻発でお蔵入りにしていたモノ。
Linuxは軽いようで、プチフリは感じない。
データが大事なので、保存用に大容量のRADIを組む。
【システム】→【システム管理】→【ディスクユーティリティー】
PalimpsestにてRAIDアレイを組む。
ミラーリング(RAID-1)
途中でストップする
mdadmが必要、とのこと。
【Synapticパッケージマネージャ】にてmdadmをインストールする。
これでRAID構成ができるようになった。
リシンクに時間がかかる。
ほったらかして寝る。
朝起きたら、まだ動いていた。
結局、10時間以上かかってリシンク終了。
左の項目からRAIDアレイの未確定領域を選択、ファイルシステムとパーティションテーブルを作成する。
ファイルシステムはext3、パーティションはGUIDとした。
これも時間がかかる。
しばらくすると完成。
クリックしてパスワードを入れるとアクセスできる。
GA-D510UDと2TBのHDD2台でRAIDを構成。
GA-D510UDはmini-ITXのマザーボードで、CPUはAtomD510である。
サーバー兼サブマシンにするため、デスクトップも使えるようにOSはUbuntu9.10にした。
GA-D510UDはRAIDが付いていている。
これが誤算。
M/BでRAIDを組めるのだが、それにアクセスするのにはドライバーが必要。
そのドライバーがWindows用しかなかった。
GIGABYTEさん、たのむよ・・・。
さっさと諦めて、ソフトRAIDとする。
32GBのSSD(SP032GBSSD650S25)があまっていたので、ここにシステムをインストールする。
以前、Windowsを入れたら、プチフリ頻発でお蔵入りにしていたモノ。
Linuxは軽いようで、プチフリは感じない。
データが大事なので、保存用に大容量のRADIを組む。
【システム】→【システム管理】→【ディスクユーティリティー】
PalimpsestにてRAIDアレイを組む。
ミラーリング(RAID-1)
途中でストップする
mdadmが必要、とのこと。
【Synapticパッケージマネージャ】にてmdadmをインストールする。
これでRAID構成ができるようになった。
リシンクに時間がかかる。
ほったらかして寝る。
朝起きたら、まだ動いていた。
結局、10時間以上かかってリシンク終了。
左の項目からRAIDアレイの未確定領域を選択、ファイルシステムとパーティションテーブルを作成する。
ファイルシステムはext3、パーティションはGUIDとした。
これも時間がかかる。
しばらくすると完成。
クリックしてパスワードを入れるとアクセスできる。
職場のPCを新装、余った部品でサーバーを作ることにしました。
OSはリリースされたばかりのUbuntu 9.04をインストール。
マザーボードのGA-K8NMF-9はオンボードのグラフィックがないので、あまっていたグラボ、GF6600GT-E256Hを付けました。GPUはnVIDIA製 GeForce 6600GT です。
設定やモニタリングには、グラフィックドライバ設定ツールnvidia-settingsを入れます。
$ sudo apt-get install nvidia-settings
システム→システム管理→NVIDIA X Server Settingsにて起動します。
ところでファンが爆音。
五月蝿い。
ファンを掃除してもだめなので、変えてみることにしました。
手元にあったのが、CoolerMasterのチップファン、CM Blue Ice。
以前使っていたのですが、グラボ交換後に干渉してしまい、そのまま引き出しに眠っていた物です。
とりあえず、強引に付けてみることにしました。

でかいので、全てのスロットルが使えなくなります。

温度を見てみます。
変更前:49℃
変更後:57℃
全然だめです。
しかもうるさい。
メリットが全くないので断念。
失敗です。
おとなしく、専用のVGAクーラーを付けることにしました。
ZAV02-NV6 Rev.2Aを購入。
取り付けは簡単です。
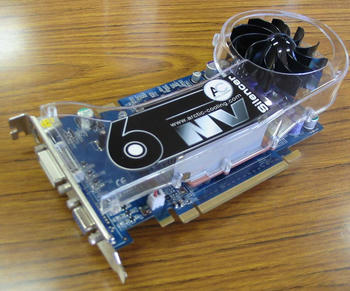
音はさすがに静か。
温度は47℃。
少し下がりました。
やはり、専用のクーラーの方がいいようです。
OSはリリースされたばかりのUbuntu 9.04をインストール。
マザーボードのGA-K8NMF-9はオンボードのグラフィックがないので、あまっていたグラボ、GF6600GT-E256Hを付けました。GPUはnVIDIA製 GeForce 6600GT です。
設定やモニタリングには、グラフィックドライバ設定ツールnvidia-settingsを入れます。
$ sudo apt-get install nvidia-settings
システム→システム管理→NVIDIA X Server Settingsにて起動します。
ところでファンが爆音。
五月蝿い。
ファンを掃除してもだめなので、変えてみることにしました。
手元にあったのが、CoolerMasterのチップファン、CM Blue Ice。
以前使っていたのですが、グラボ交換後に干渉してしまい、そのまま引き出しに眠っていた物です。
とりあえず、強引に付けてみることにしました。
でかいので、全てのスロットルが使えなくなります。
温度を見てみます。
変更前:49℃
変更後:57℃
全然だめです。
しかもうるさい。
メリットが全くないので断念。
失敗です。
おとなしく、専用のVGAクーラーを付けることにしました。
ZAV02-NV6 Rev.2Aを購入。
取り付けは簡単です。
音はさすがに静か。
温度は47℃。
少し下がりました。
やはり、専用のクーラーの方がいいようです。
最新記事
(02/09)
(06/06)
(05/31)
(05/19)
(04/10)
カテゴリー
最新トラックバック
Amazon
最新コメント
[05/24 グッチ 時計 メンズ]
[11/22 ココ シャネル 歌]
[07/23 ロレックス gmtマスター2 青黒 小説]
[07/23 スーパーコピー 時計 カルティエ]
[07/23 スーパーコピー iphone]
プロフィール
HN:
Scorpionfish
性別:
男性
趣味:
PC・釣り・山登り・自転車・走ること・そして酒
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
ブログ内検索
アクセス解析
カウンター

